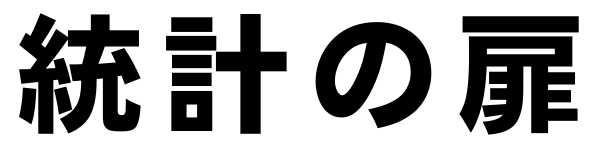資料解釈とは?またそのコツ
公務員試験の資料解釈は、データや数値を含む表やグラフを基に情報を分析し、正確な結論を導き出す能力を問う問題です
政策立案や行政運営では、膨大なデータを正確に解釈し、根拠に基づく判断が求められます。このため、資料解釈能力は公務員にとって欠かせないスキルです。本記事では、その重要性と問題の解き方を詳しく解説します。
どんなパターンがあるのか
資料解釈の問題にはいくつかの典型的なパターンがあります。主なパターンを以下に紹介します。
- 表を用いた問題:
- 数値データが表形式で与えられ、そのデータをもとに計算や比較を行う問題です。
例:人口統計、売上高、経済指標などの数値データ。
- 数値データが表形式で与えられ、そのデータをもとに計算や比較を行う問題です。
- グラフを用いた問題:
- 折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフなどの視覚的データを分析する問題です。
例:売上の推移グラフ、人口構成比の円グラフなど。
- 折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフなどの視覚的データを分析する問題です。
- 図表を用いた問題:
- 表とグラフが組み合わさった複合的な資料を読み解く問題です。
例:複数の指標を含む経済レポートなど。
- 表とグラフが組み合わさった複合的な資料を読み解く問題です。
- 文章と資料の組み合わせ問題:
- 文章中に数値やデータが散りばめられており、それをまとめて分析する問題です。
例:レポートや調査結果の一部を基にした問題。
- 文章中に数値やデータが散りばめられており、それをまとめて分析する問題です。
解く時のコツ
資料解釈の問題を効率よく解くためのコツをいくつか紹介します。
- 資料をよく読む:
- まず、与えられた資料全体をざっと目を通し、どのようなデータが含まれているかを把握します。
- 資料の種類や構成要素を理解することが重要です。
- 設問をよく読む:
- 質問内容を正確に理解し、何を問われているのかを明確にします。
- 質問に対する答えを導くための情報が資料内のどこにあるのかを特定します。
- 計算ミスに注意:
- 資料解釈では計算が求められることが多いため、計算ミスを防ぐために丁寧に計算します。
- 計算過程をメモし、見直すことでミスを防ぎます。
- 必要な情報を抜き出す:
- 質問に答えるために必要な情報を資料から抜き出し、不要な情報に惑わされないようにします。
- 質問に答えるために必要な情報を資料から抜き出し、不要な情報に惑わされないようにします。
- 時間配分を考える:
- 資料解釈は時間がかかることが多いため、時間配分を考えて効率よく進めます。
- 優先順位をつけて、解ける問題から解くことが重要です。
資料解釈(例題とその解説)
ここでは具体的な例題を示し、その解き方を解説します。
例題
以下の表は、ある国のA市とB市における過去5年間の出生数を示しています。
| 年度 | A市 出生数 | B市 出生数 |
|---|---|---|
| 2019 | 1,200 | 1,800 |
| 2020 | 1,250 | 1,750 |
| 2021 | 1,300 | 1,700 |
| 2022 | 1,350 | 1,650 |
| 2023 | 1,400 | 1,600 |
問1:A市とB市の出生数の合計が最も多かった年度はどれですか?
問2:A市の出生数の増加率が最も高かった年度はどれですか?
問1 解説
- 資料を確認:
- 表から各年度のA市とB市の出生数を確認します。
- 一番左の列が”年度”を表し、一番上の行が”出生数”を表す。
- 合計を計算:
- 各年度のA市とB市の出生数を合計します。
- 2019年:
- 2020年:
- 2021年:
- 2022年:
- 2023年:
- 2019年:
- 各年度のA市とB市の出生数を合計します。
- 合計を比較:
- 各年度の合計出生数を比較すると、すべての年度で出生数の合計は同じ
- 各年度の合計出生数を比較すると、すべての年度で出生数の合計は同じ
- 答えを導出:
- A市とB市の出生数の合計が最も多かった年度はすべての年度(2019年~2023年)です。
問2 解説
- 資料を確認:
- 表から各年度のA市の出生数を確認します。
- 表から各年度のA市の出生数を確認します。
- 増加率を計算:
- 増加率 = (今年の出生数 – 昨年の出生数) / 昨年の出生数 × 100%
- 2020年:
- 2021年:
- 2022年:
- 2023年:
- 2020年:
- 増加率 = (今年の出生数 – 昨年の出生数) / 昨年の出生数 × 100%
- 増加率を比較:
- 各年度の増加率を比較すると、最も高いのは2020年の
- 各年度の増加率を比較すると、最も高いのは2020年の
- 答えを導出:
- A市の出生数の増加率が最も高かった年度は2020年です。
おわりに
以上が、公務員試験における資料解釈の問題についての概要、パターン、解く際のコツ、および例題とその解説です。これらのポイントを押さえて勉強を進めることで、資料解釈の問題に対する対応力を高めることができます。
さいごまで読んでいただきありがとうございました!
『統計の扉』で書いている記事
- 高校数学の解説
- 公務員試験の数学
- 統計学(統計検定2級レベル)
ぜひご覧ください!
数学でお困りの方は、コメントやXでご連絡ください。(Xはこちら)
私自身、数学が得意になれたのはただ運が良かったんだと思っています。たまたま親が通塾させることに積極的だったり、友達が入るって理由でそろばんに入れたり、他の科目が壊滅的だったおかげで数学が(相対的に)得意だと勘違いできたり。
”たまたま”得意になれたこの恩を、今数学の学習に困っている人に還元できたらなと思っています。お金は取りません。できる限り(何百人から連絡が来たら難しいかもですが…)真摯に向き合おうと思っていますのでオアシスだと思ってご連絡ください。