公務員試験の数学の範囲
「公務員試験を受けようと思ってるけど、数学が苦手…」
こんな悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
本稿では、どうすれば数学分野を効率よく対策できるのかをまとめていきます!
国家公務員であれ、地方公務員であれ、公務員試験の受験科目というのはほぼ共通です。
択一式の「教養試験」と「専門試験」、それと記述式の「論文」に面接による「人物試験」があるのがほとんどでしょう。このうち択一式の教養試験をさらに細かく分類していくと、「一般知能」と「一般知識」に分けることができます。
数学が必要となる科目は?
一般知能では「文章理解」と「数的処理」が問われ、一般知識では「社会科学」「自然科学」「人文科学」「時事」が問われています。
さて、ここで数学が公務員試験のどこに関連してくるかといいますと、一般知能の数的処理と一般知識の自然科学のふたつになります。それぞれのどのようなかたちで数学が必要になってくるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
数的処理とは?
数的処理とは、さらに判断推理・数的推理・資料解釈に細かく分類されます。公務員としての必要な事務処理能力を問う問題になります。主に、問題文を読み込み、論理的に思考・計算して、そこから短時間で答えにたどり着くことが求められます。
例えば、一般知能の数的処理では、数学で必要となってくる論理的思考を要する設問と、数学の計算そのものが問われるような設問があります。前者は「すべてAはBである」「CはAである」という命題から「CはBである」という結論を導くような、論理的思考方法が試される問題です。
出題分野は以下のとおりです。
・約数、倍数
・整数
・比と割合
・利益
・濃度
・記数法
・覆面積、魔方陣
・その他の文章題(ニュートン算、仕事算、集合算、年齢算、平均算)
・場合の数
・確率
・図形の計量
>>詳細はこちらから
自然科学とは?
公務員は法律に従って仕事をしなければならないので、欠くべからざる能力として公務員試験ではこのような論理的な力が問われます。
自然科学は問題文を読解して方程式を作り、速度を計算したり液体の濃度を求めたりといった、まさに学校で習ったような数学の設問です。一般知識の自然科学の分野では、物理や化学の知識が問われるものもあります。当然、これらの設問に答えるためにも数学的な能力が必要となってくることは言うまでもありません。
公務員試験の数学のレベルはどれくらい?
公務員試験の数学のレベルはどれくらいなのでしょうか。
公務員の数学は難しくても高校程度のレベルと言えます。
公務員試験では【数学】の出題数は、基本的に1~2問と少ないですが、数学の要素を含んだ【数的処理】の問題は多いです。数的処理とは【数的推理】【判断推理】【資料解釈】をまとめたものです。数的処理は問題数が多いため、苦手なままにせず、しっかり対策することが必要になります。つぎに、公務員試験の数学対策についてみていきましょう。
公務員試験での数学対策
では、数学が苦手というひとはどのように公務員試験対策を練ればよいのでしょうか。
主な職種の「数的推理」の出題数です。
※2022年の本試験データに基づくものです。
| 教養科目 | 科目一覧 | 国家一般職 | 地方上級 | 市役所 |
|---|---|---|---|---|
| 数的処理 | 判断推理 | 8 | 9 | 7 |
| 数的推理 | 5 | 6 | 5 | |
| 資料解釈 | 3 | 1 | 1 | |
| 自然科学 | 数学 | 0 | 1 | 1 |
| 物理 | 1 | 1 | 1 | |
| 化学 | 1 | 2 | 1 | |
| 生物 | 1 | 2 | 1 | |
| 地学 | 0 | 1 | 2 |
もちろんすべての科目をまんべんなく勉強することができれば言うことありませんが、試験科目は多岐にわたるのでもっと効率よく時間を使いたいというのも正直な気持ちでしょう。そこで「数的処理以外の数学については勉強をあきらめる」というのもひとつの作戦となるのではないでしょうか。
数的処理のみに時間をかけて効率的に対策をする
まず、自然科学の物理や化学は1問ずつくらいしか出題されないわりには勉強範囲が広く、公務員試験の受験者のほとんどが苦手とするので、スッパリとあきらてもいいかもしれません。
その一方で、数的処理については受験者がみな問題集などでみっちり対策を練ってくるので、数学が苦手なひとは差がつかないように時間をかけて練習するようにしましょう。ある程度問題をこなせばコツがつかめてきて、どんな問題にも対応できるようになってくるので、物理や化学とは違って時間をかける意味があります。
「数的処理」は、出題数が他の科目と比べて多い科目です。教養試験はどの職種でも必須とされています。出題数が多く、さらに必ず出題されるため、「数的処理」の対策はどの試験でも重要となります。
公務員試験の数学対策におすすめな参考書3つ
つぎに、公務員試験の数学対策におすすめな本をご紹介します。ぜひ、参考にしてください。
おすすめの参考書①
おすすめの参考書1つめは、TAC出版が出版している【地方初級・国家一般職(高卒者)問題集 数学・数的推理 第2版】です
本のタイトルにもあるように、地方初級・国家一般職(高卒程度)の受験を考えている人におすすめといえるでしょう。この本では、平易な問題から応用的な問題までバランスよく掲載しています。この本で繰り返し演習をすれば数学・数的推理の実力は身につくでしょう。
おすすめの参考書②
おすすめの参考書2つめは、実務教育出版が出版している【数的推理がみるみるわかる! 解法の玉手箱 改訂第2版】です。
最新の出題傾向に対応し、問題の解き方を詳しく解説しています。算数・数学が苦手だと感じている人も、扱いやすく分かりやすい本だといえるでしょう。この本は高卒程度から大卒・院卒程度の試験まで幅広く対応しています。
おすすめの参考書③
おすすめの参考書3つめは、【公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 数的推理】です。
この本も、上記と同じ実務教育出版が出版しています。この本のシリーズは累計350万部突破しているようです。そのため、公務員試験を受験する人たちにとって、このシリーズは支持されているといえるでしょう。また、国家総合職や国家一般職、地方上級などの過去問を287問収録しています。
公務員試験で数学が必要となる数的処理は時間をかけて対策をしよう
以上のように公務員試験では数学の知識が必要となってきます。これは論理的に物事を考える必要にせまられる公務員となる以上、避けては通れないことです。実務で方程式を使うことだってありますので、あのときやっておけばと後悔しないためにもしっかり勉強をしておきましょう。
おわりに
公務員試験を突破するために数的処理/自然科学をどう対策していくかが重要になってきます。
また、学生時代数学が苦手だった方にとって自分の力だけで解決していくのは至難の業です。専門家の力を借りながら頑張っていきましょう!
さいごまで読んでいただきありがとうございました!
- 大学受験数学で困っている方
- 公務員試験の数学で困っている方
- 統計学(統計検定)の勉強で困っている方
個人家庭教師やってるので、ぜひコメントやXでご連絡ください。(Xはこちら)
私自身、数学に関して順風満帆に理解できてきたわけではありませんでした。
周りを見渡せば数学の天才がゴロゴロいて、そんな人たちに比べれば私は足元にも及びませんでした。
だからこそ、わからない、理解できない方の気持ちを少しはわかってあげられると自負しております。
数学に困っている方の一助になれれば幸いです。
ご連絡お待ちしております。

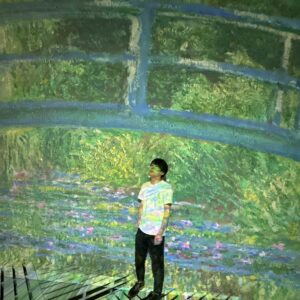

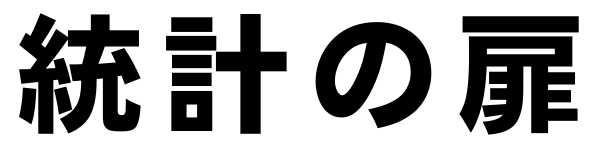




質問や感想はコメントへ!